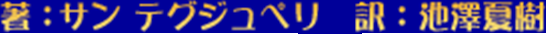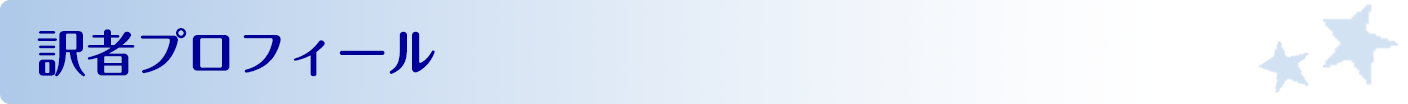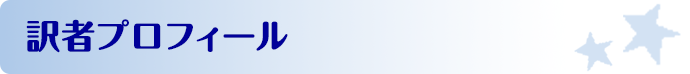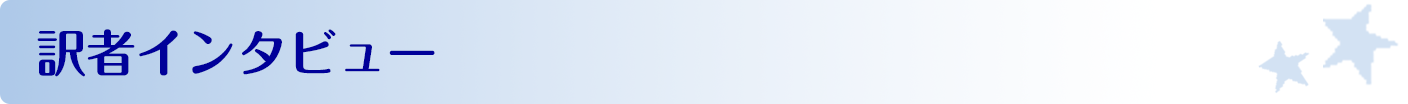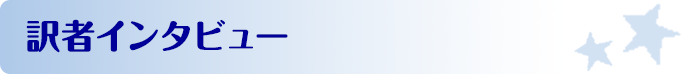池澤夏樹(いけざわ・なつき)

池澤夏樹(いけざわ・なつき)
1945年北海道生まれ。埼玉大学理工学部物理学科中退。1975年より3年間ギリシャに滞在。 詩作、評論から作家活動に入る。1988年に発表した「スティル・ライフ」により芥川賞、「母なる自然のおっぱい」により読売文学賞、 「マシアス・ギリの失脚」により谷崎賞を受賞。1994年沖縄移住。近著に「イラクの小さな橋をわたって」「静かな大地」など。 2005年「パレオマニア」で桑原武夫学芸賞を受賞。
『星の王子さま』を訳すという幸運
この本のこととなると、誰もが最初に読んだ時の思い出からはじめる。
その例にならえば、ぼくの場合は小学校の3年生くらいの頃だったと思う。岩波少年文庫の一冊として刊行された版を伯母が買ってくれた。
北大の理科系の研究者だったこの伯母にはたくさん本を買ってもらった。時おり札幌から東京のぼくのところに何冊かの本が入った楽しい小包が届いた。
伯母は買った本を必ず自分で読んでから送る習慣だったので、会った時にはその本について話すことができた。母もぼくの手から奪うようにして読んだから、
学会などで伯母が上京した時には本をめぐって3人の会話が成り立った。
ではあの頃、ぼくは『星の王子さま』をどう読んだのだろう。強い魅力を感じたことはまちがいない。
だからぼくはこの本をずっと持ち歩いて、何度となく読み返した。しかし、何度読んでもわからない部分が残った。
内容に何か掴みきれないものがあって、それゆえに、また数年後に立ち返る。
懐かしさに駆られてまた読みながら、やはりおぼろな謎のようなものが残る。
これが『宝島』ならば、ジム・ホーキンスの母親が経営する宿に老水夫が現れる巻頭の場面から、
あの「八銀貨!八銀貨!」という悪夢を思い返す終末まで、わからないところなどはない。
すべては明快で、知らない言葉さえわかればストーリーは子供の頭にもすなおに入る。
だが、『星の王子さま』はちがうのだ。明晰ではあるけれども、決して明快ではない。
いつになってもこの話から卒業できなかったのはそのためだし、翻訳をしないかと集英社から持ちかけられた時にすぐに受けたのもそのためだ。
なぜならば、翻訳というのはつまり精読だから。
訳してみてわかったのは、これが散文ながらとても詩的な文体を持った作品であるということ。
少ない言葉に多くの含意がある。言葉の表面の意味以上のことを伝えようとしている。
ただの比喩を超えて寓話のような話法が多く、それはたぶん理解するものではなくて感得するものなのだ。
子供にも読める一方で、どんな大人でもすべてを読み取ったとは言えない。そして、この点にこそ、強い魅力がある。
日本の文学の中でいちばん似たものを選ぶならば、宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』になるだろう。
どちらも少年(たち)が星の間を旅する話だし、その旅路を通じて何かを学ぶ話であり、ずっと一緒にいたいと願いながら別れる話だ。
そして、どちらも死をめぐる話でもある。
翻訳という作業はおもしろかった。一行ごとに自分の日本語のスキルの限界を試されている気がした。
フランス語のセンテンスの意味は取れる。しかしそれに対応する日本語のセンテンスはそう簡単には作れない。
この話にはいくつかのキーワードがある。キーワードには意味の幅がある。それらすべてで意味の重なる日本語のキーワードを発見できるかどうか。
ぼくはできるだけ言葉数をけずった。作者が五語で言ったことは五語で訳したい。
間延びしてリズムを崩してはいけない。なぜならこれは半分までは詩だから。
似たような翻訳をぼくはまったく別の分野の翻訳で経験している。
テオ・アンゲロプロスの映画の字幕制作という仕事で、あの圧縮されたギリシャ語に込められた意味をごく短い日本語に写す訓練を20数年に亘ってやってきた。
それが今回はずいぶん役に立ったと思った。
タイトルについて説明しておきたい。ぼくの訳でも内藤濯が作った『星の王子さま』というタイトルをそのまま使うことになった。
この邦題は優れている。実際の話、これ以外の題は考えられない。これには日本語の根幹にかかわる理由がある。
原題を直訳すれば、『小さな王子さま』ということになるだろうけれど、元のpetitに込められた親愛の感じはそのままでは伝わらない。
タイトルなのだからもう一つ、主人公を特定する形容が欲しい。
そして、こういう時に日本では古来、その人が住むところの地名を冠した。
「桐壺の更衣」も「清水の次郎長」もこのゆかしい原理から生まれた呼び名であり、
「星の王子さま」もこの原理に沿った命名だからこそ、定訳となったのだ。
『集英社文芸雑誌 青春と読書より』